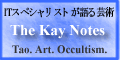「我流」と言ったら、どこかヤクザな(粗末でつまらない)印象があるかもしれないが、本物の実力者は皆我流だ。
あまりの上手さに悪魔と契約していたのではと言われたヴァイオリンの名手バガニーニの演奏技術は我流だったし、アインシュタインは大学生時代、大学の講義には一度も出席せず独学で勉強したが、これも我流と言える。
ところが、現代人は、子供の時から、教わった通りにやる、教わった通りにしか出来ない者が多い。
最悪なのは受験で、日本の受験は闇の勢力が日本人の若者の頭を悪くするために作った制度ではないかと疑いたくなるほどだ。
私は、ある一流中学の理科の受験問題を解いたことがあるが、いきなりやったら、理系の大学生でも解けないような問題だった。
では、これを解ける小学生の頭がそれほど良いのかというと、受験生は小学3~4年生くらいから、膨大な時間をかけて受験問題を解くためだけの訓練をするのであるが、それは、ひたすら教えられたパターンを憶えるだけで、ある程度の地頭は必要かもしれないが、それは頭が良くなる訓練ではなく、ひょっとしたらというか、おそらく悪くなると思う。
なんという時間とエネルギーの無駄と個人的には呆れる(本音ではただの馬鹿の所業と思うが、こんな意見は個人的見解と言わないといけないらしい)。
アインシュタインは学校では劣等生で、大学受験に合格出来ず、制度を利用して無試験で大学に入ったのだ。
笹沢佐保の時代劇小説『木枯らし紋次郎』では、紋次郎は貧しい農家の出身で、10歳で家を出て、流れ者の渡世人(博打打)になった。
そんな紋次郎は、いくら剣の腕が立つとはいえ、正式に剣を習ったことなどあるはずもなく、勘と度胸の喧嘩剣法だった。
そんな紋次郎は、そこそこまでの武士になら勝ったが、本物の達人相手には、まともに戦っては勝ち目がなかった。
だが、剣の達人相手との決闘は、見所になっており、何度も描かれている。
そして、最後に勝つのは紋次郎である。勝負というのは、総合的なものであり、剣技で劣るなら別のことで工夫をすれば良いのである。
つまり、紋次郎は剣の達人ではなくても決闘の達人、喧嘩の達人なのであり、それは紋次郎の我流である。
私のコンピュータプログラミングも我流だが、普通のプログラマーよりは上手いと思う。
私は、プログラミングを学校で教えてもらおうとする者とは、ちょっと付き合いたくない。
もちろん、我流であっても、優れた能力者に学ぶのは疑いなく良いことだが、手取り足取り教えてもらおうとする者に見込みはない。
しかし、今の落ちぶれた日本では、手取り足取り教えるというスタイルが浸透し、実は、それこそが日本を駄目にしたのかもしれない。
優れた能力者の技術・手法・コツは見て憶えるものであり、それは教わるものではない。
日本では昔から、あらゆる分野で、師匠の技は盗むものであり、それは、見て憶えるものだと言われてきた。
その良さがなくなっており、師匠も金儲けのために親切丁寧に教えることが多くなっている。
昨日も書いたが、佐川幸義は自分の四股を見せさえせず、ごく一部を教えることで後は弟子に工夫させたが、それこそが最も良いものを修得出来る方法である。

AIアート438
「朝日」
Kay
腕振り運動も佐川幸義流四股も、基本は同じで、リラックスすること、なるべく長時間やること、そして、静かにやることだと思う。
後は、名人のやることを、見たり、読んだりしながら、自分で工夫してこそ、本当に良いやり方が分かる。
引き寄せなども全くそうだろう。
誰かのやる通りにやろうとし、そのようにしてうまくいかないのは当たり前である。
しかし、教えられた通りにやって楽に得をしようという、岡本太郎流に言えば卑しい者が多いのである。
我流だと、初めは失敗することも多く、ものによっては何年も無駄な努力をする羽目になる。
だが、無駄な努力ほど尊いものはない(受験はそうではないと思うが、ある意味ではそうかもしれない)。
深呼吸は、最も重要なものでありながら、自分流が最も似合うものだと思う。
あまりの上手さに悪魔と契約していたのではと言われたヴァイオリンの名手バガニーニの演奏技術は我流だったし、アインシュタインは大学生時代、大学の講義には一度も出席せず独学で勉強したが、これも我流と言える。
ところが、現代人は、子供の時から、教わった通りにやる、教わった通りにしか出来ない者が多い。
最悪なのは受験で、日本の受験は闇の勢力が日本人の若者の頭を悪くするために作った制度ではないかと疑いたくなるほどだ。
私は、ある一流中学の理科の受験問題を解いたことがあるが、いきなりやったら、理系の大学生でも解けないような問題だった。
では、これを解ける小学生の頭がそれほど良いのかというと、受験生は小学3~4年生くらいから、膨大な時間をかけて受験問題を解くためだけの訓練をするのであるが、それは、ひたすら教えられたパターンを憶えるだけで、ある程度の地頭は必要かもしれないが、それは頭が良くなる訓練ではなく、ひょっとしたらというか、おそらく悪くなると思う。
なんという時間とエネルギーの無駄と個人的には呆れる(本音ではただの馬鹿の所業と思うが、こんな意見は個人的見解と言わないといけないらしい)。
アインシュタインは学校では劣等生で、大学受験に合格出来ず、制度を利用して無試験で大学に入ったのだ。
笹沢佐保の時代劇小説『木枯らし紋次郎』では、紋次郎は貧しい農家の出身で、10歳で家を出て、流れ者の渡世人(博打打)になった。
そんな紋次郎は、いくら剣の腕が立つとはいえ、正式に剣を習ったことなどあるはずもなく、勘と度胸の喧嘩剣法だった。
そんな紋次郎は、そこそこまでの武士になら勝ったが、本物の達人相手には、まともに戦っては勝ち目がなかった。
だが、剣の達人相手との決闘は、見所になっており、何度も描かれている。
そして、最後に勝つのは紋次郎である。勝負というのは、総合的なものであり、剣技で劣るなら別のことで工夫をすれば良いのである。
つまり、紋次郎は剣の達人ではなくても決闘の達人、喧嘩の達人なのであり、それは紋次郎の我流である。
私のコンピュータプログラミングも我流だが、普通のプログラマーよりは上手いと思う。
私は、プログラミングを学校で教えてもらおうとする者とは、ちょっと付き合いたくない。
もちろん、我流であっても、優れた能力者に学ぶのは疑いなく良いことだが、手取り足取り教えてもらおうとする者に見込みはない。
しかし、今の落ちぶれた日本では、手取り足取り教えるというスタイルが浸透し、実は、それこそが日本を駄目にしたのかもしれない。
優れた能力者の技術・手法・コツは見て憶えるものであり、それは教わるものではない。
日本では昔から、あらゆる分野で、師匠の技は盗むものであり、それは、見て憶えるものだと言われてきた。
その良さがなくなっており、師匠も金儲けのために親切丁寧に教えることが多くなっている。
昨日も書いたが、佐川幸義は自分の四股を見せさえせず、ごく一部を教えることで後は弟子に工夫させたが、それこそが最も良いものを修得出来る方法である。

AIアート438
「朝日」
Kay
腕振り運動も佐川幸義流四股も、基本は同じで、リラックスすること、なるべく長時間やること、そして、静かにやることだと思う。
後は、名人のやることを、見たり、読んだりしながら、自分で工夫してこそ、本当に良いやり方が分かる。
引き寄せなども全くそうだろう。
誰かのやる通りにやろうとし、そのようにしてうまくいかないのは当たり前である。
しかし、教えられた通りにやって楽に得をしようという、岡本太郎流に言えば卑しい者が多いのである。
我流だと、初めは失敗することも多く、ものによっては何年も無駄な努力をする羽目になる。
だが、無駄な努力ほど尊いものはない(受験はそうではないと思うが、ある意味ではそうかもしれない)。
深呼吸は、最も重要なものでありながら、自分流が最も似合うものだと思う。