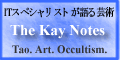昔、ひろさちやさんの本で読んだだけだが、イスラム教徒は「インシャーアッラー」という言葉をよく使うらしい。
これは「もし神の思し召しがあれば」という意味で、例えば、明日の午後3時に待ち合わせをしようという合意をした後で「インシャーアッラー」と言う。
ところが、翌日、片方が時間に遅れてしまったが、遅れた方は、「神の思し召しがなかったから遅れた」と堂々と言う。
金を借りても同様で、「〇月×日に返そう。もし神の思し召しがあれば」と言い、返せなくなっても、「俺は返すつもりだったが、返すことが神の思し召しでなかった」と言えば良いのである。
こういう話をすると、決まって、「それええなあ」という感じで受け取り、「へーんだ!俺が約束を果たせないのは神の思し召しでなかったからなんだよー」と相手をあざ笑う態度を取れば良いのだと思う馬鹿がいる。そんな人間に見込みはない。
だが、先日のロシアのプーチン大統領の演説ではないが、相手を尊重する気持ちを大切にすれば、このやり方で、非常に平和な世界になるのではと思う。
相手を尊重しないのは、尊大で自己中心的に考えるからであり、根本的には欲張りなのだ。
今の世の中では、相手が欲張りでないことは求め難い。みんな、すっかり欲張りになってしまった。
だが、自分のことは、「もし神の思し召しであれば」と思うことは良いことである。
しかし、ここで重要なことがある。
それは、ニーチェが「運命愛」と呼んだもので、どんな運命であれ、それは自分の意志でもあるとすることだ。
アイルランドの詩聖W.B.イェイツも同じ考え方をしており、イェイツの方が分かり易いかもしれない。
つまり、あらゆることは神の意志で起こるが、神の意志を自分の意志でもあるとした時に、自分が神に限りなく近づく。
それが神になる方法であり、また、アインシュタインが言ったように、「神は老獪である。だが悪意はない」のであり、全てはよくなる。

AIアート453
「花の時」
Kay
とはいえ、思考があるままでは、なかなかそうは思えない。
ひどく嫌な目にあった時、「これは神の意志であり、私の意志でもある」と思おうとしても、本心ではそう思っていないので、それは嘘になってしまう。
思考があると、ビートルズの『イエスタデイ』のように、「なぜ彼女は行ってしまったんだ」と嘆き、「それが神の意志であり、自分の意志でもある」などとは、とても思えない。
だが、思考を消し、積極的に同意しないまでも、静かにしていれば、彼女は実はひどい女であったと分かったり、あるいは、もっと素晴らしい恋人が出来るかもしれない。そんなことはよくあるだろう。
深呼吸を心掛け、思考を消していけば、自我の愚かしい願いは叶わないかもしれないが、それが何かは今は全く分からなくても、最高の恵みが得られるだろう。
これは「もし神の思し召しがあれば」という意味で、例えば、明日の午後3時に待ち合わせをしようという合意をした後で「インシャーアッラー」と言う。
ところが、翌日、片方が時間に遅れてしまったが、遅れた方は、「神の思し召しがなかったから遅れた」と堂々と言う。
金を借りても同様で、「〇月×日に返そう。もし神の思し召しがあれば」と言い、返せなくなっても、「俺は返すつもりだったが、返すことが神の思し召しでなかった」と言えば良いのである。
こういう話をすると、決まって、「それええなあ」という感じで受け取り、「へーんだ!俺が約束を果たせないのは神の思し召しでなかったからなんだよー」と相手をあざ笑う態度を取れば良いのだと思う馬鹿がいる。そんな人間に見込みはない。
だが、先日のロシアのプーチン大統領の演説ではないが、相手を尊重する気持ちを大切にすれば、このやり方で、非常に平和な世界になるのではと思う。
相手を尊重しないのは、尊大で自己中心的に考えるからであり、根本的には欲張りなのだ。
今の世の中では、相手が欲張りでないことは求め難い。みんな、すっかり欲張りになってしまった。
だが、自分のことは、「もし神の思し召しであれば」と思うことは良いことである。
しかし、ここで重要なことがある。
それは、ニーチェが「運命愛」と呼んだもので、どんな運命であれ、それは自分の意志でもあるとすることだ。
アイルランドの詩聖W.B.イェイツも同じ考え方をしており、イェイツの方が分かり易いかもしれない。
つまり、あらゆることは神の意志で起こるが、神の意志を自分の意志でもあるとした時に、自分が神に限りなく近づく。
それが神になる方法であり、また、アインシュタインが言ったように、「神は老獪である。だが悪意はない」のであり、全てはよくなる。

AIアート453
「花の時」
Kay
とはいえ、思考があるままでは、なかなかそうは思えない。
ひどく嫌な目にあった時、「これは神の意志であり、私の意志でもある」と思おうとしても、本心ではそう思っていないので、それは嘘になってしまう。
思考があると、ビートルズの『イエスタデイ』のように、「なぜ彼女は行ってしまったんだ」と嘆き、「それが神の意志であり、自分の意志でもある」などとは、とても思えない。
だが、思考を消し、積極的に同意しないまでも、静かにしていれば、彼女は実はひどい女であったと分かったり、あるいは、もっと素晴らしい恋人が出来るかもしれない。そんなことはよくあるだろう。
深呼吸を心掛け、思考を消していけば、自我の愚かしい願いは叶わないかもしれないが、それが何かは今は全く分からなくても、最高の恵みが得られるだろう。